じつは「アメリカ軍」はほくそ笑んでいた…ついに「日本」で実現してしまった「アメリカのヤバすぎる思惑」
日本がアメリカの支配下にあるという明確な条文が明らかになる
日本には、国民はもちろん、首相や官僚でさえもよくわかっていない「ウラの掟」が存在し、社会全体の構造を歪めている。そうした「ウラの掟」のほとんどは、アメリカ政府そのものと日本とのあいだではなく、じつは米軍と日本のエリート官僚とのあいだで直接結ばれた、占領期以来の軍事上の密約を起源としている。最高裁・検察・外務省の「裏マニュアル」を参照しながら、日米合同委員会の実態に迫り、日本の権力構造を徹底解明する。
*本記事は矢部 宏治『知ってはいけない 隠された日本支配の構造』(講談社現代新書)から抜粋・再編集したものです。
———-
アメリカは「国」ではなく、「国連」である
こうして指揮権密約の歴史をさかのぼったことで、戦後、日米のあいだで結ばれた無数の軍事的な取り決めの、大きな全体像が見えてきました。その重要な手がかりとなったのが、朝鮮戦争のさなかにつくられた、米軍が自分で書いた旧安保条約の原案だったのです(1950年10月27日案)。
この原案の中にあった指揮権に関する条文については、すでにお話ししました。
では、基地権については、そこではどのように書かれていたのでしょう。
「第2条 軍事行動権」と題されたその条文を見てみると、左のようにそこには日米安保の本質が、やはり非常に明快に表現されていたのです(以下、同2条から要点を抜粋。〔 〕内は著者の解説。https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1950v06/pg_1337)。
「米軍原案」の基地権条項
○ 日本全土が防衛上の軍事行動のための潜在的地域とみなされる。
〔これがいわゆる「全土基地方式」のもとになった条文です。米軍が日本国内で、どこに基地を置こうと、どんな軍事行動をしようと、日本側は拒否できないということです〕
○ 米軍司令官は必要があれば、日本政府へ通告したあと、軍の戦略的配備を行う無制限の権限を持つ。
〔他国(日本)への軍の配備について「無制限の権限を持つ」とは、スゴい表現です。この条文とその前の「全土基地方式」の条文が「アメリカは、米軍を日本国内およびその周辺に配備する権利を持つ」という旧安保条約・第1条のもとになっています〕
○ 軍の配備における根本的で重大な変更は、日本政府との協議なしには行わないが、戦争の危険がある場合はその例外とする。
〔核兵器の配備など「重大な変更」については、米軍は日本政府との「協議なしには行わない」と書かれています。しかしこの表現は「合意なしには行わない」とは違って、日本の意向だけでは拒否できないという意味でもあるのです。さらに戦争の危険があるときは、核の地上配備だろうとなんだろうと、日本側と協議などまったくしないという方針が、はっきりと書かれています。
これが日米安保の本質です。そしてその本質を国民の目から隠すために、これまで多くの日本の首相たちが、アメリカとの「核密約」や「事前協議密約」を結び続けてきたのです〕
○ 平時において米軍は、日本政府へ通告したあと、日本の国土と沿岸部で軍事演習を行う権利を持つ。
〔戦争の危険性がまったくないときでも、米軍は日本政府に一方的に「通告」すれば、日本全土とその沿岸部で自由に軍事演習を行うことができるということです。「協議」をする必要もない。この条文こそが、まさに2020年以降、日本全土で始まろうとしている危険なオスプレイによる低空飛行訓練の正体なのです〕
日本の戦後を貫く方程式
このように、米軍が書いたこの旧安保条約の原案には、指揮権についても基地権についても、非常にリアルな日米安保の本質が記されています。
そしてこの「米軍原案」と、第5章でお話しした「密約の方程式」を組みあわせれば、その後70年近くのあいだに日米間で起きた無数の軍事上の出来事を、すべてひとつの大きな流れのなかに位置づけることができるのです。
思い出していただきたいのですが、戦後の日米間の軍事上の取り決めを貫く基本法則は次のとおりでした。
「古くて都合の悪い取り決め」=「新しくて見かけのよい取り決め」+「密約」
そして1950年10月の「米軍原案」が、その後わずかな訂正だけで正式な日米交渉の場に提出されたという事実を考えあわせると、戦後、日米間で結ばれたすべての条約、協定、密約を、具体的な条文レベルで次のように整理することができるのです。
「米軍自身が書いた旧安保条約の原案」=「戦後の正式な条約や協定」+「密約」
この式にあてはめてみると、これまで不思議でしかたがなかった、ほとんどの謎がスッキリ解けてしまいます。軍事面からみた「戦後日本」の歴史とは、つまりは米軍が朝鮮戦争のさなかに書いたこの安保条約の原案が、多くの密約によって少しずつ実現されていく、長い一本のプロセスだったということができるでしょう。
そのもっとも典型的な例が、2015年に大問題となった安保関連法でした。前章で述べたとおり、この1950年10月の「米軍原案」に書かれていた海外派兵についての条文が、なんと65年もの時を経て、ついにあのとき、オモテの国内法として成立してしまったわけです。
もちろん、歴代の首相や大臣、官僚のなかには、この大きな流れに抵抗しようとした人もいれば、積極的に推し進めることで個人的な利益を得ようとした人もいたでしょう。
しかしその無数の人間ドラマもまた、軍事面から見れば、この米軍原案が長い時間をかけて少しずつ実現していくプロセスの一コマでしかなかった。それが日本の戦後史だったということです。
悲しい現実ですが、事実はきちんと見たほうがいい。事実を知り、その全体像を解明するところからしか、事態を打開する方策は生まれてこないからです。反対運動でその違法なプロセスの進行を遅らせているあいだに、その法的な構造を体系的に解明し、根本的な解決策を考えださなければならないのです。
じつは安保条約での集団的自衛権を拒否し続けていたアメリカ
たとえば2015年の安保関連法案の国会審議のとき、大きな焦点となった集団的自衛権の問題があります。あのとき国会前のデモでは、若い学生のみなさんが中心となって、
「憲法まもれ」
「安倍はやめろ」
といったコールを連日繰り返していました。私も何度か行って声を張り上げましたが、
「集団的自衛権はいらない」
というコールだけは、一緒に言えませんでした。
なぜなら1951年1月末から始まった日米交渉のなかで、旧安保条約をなんとか国連憲章の集団的自衛権にもとづく条約にしようと、必死で交渉していたのが日本側のほうで、それを一貫して拒否しつづけていたのがアメリカ側だったことを、私はよく知っていたからです。
そしてその両者の関係は、のちの安保改定においても、基本的に変わることはありませんでした。
NATOと「日米同盟」の違い
いったいそれは、どういうことなのか。
事実、肥田進・名城大学名誉教授(日本におけるジョン・フォスター・ダレス研究の第一人者)の分類を見ると、かつてアメリカが集団的自衛権にもとづく安全保障条約を結んだのは、彼らにとって死活的に重要な意味をもつ中南米(米州機構)とヨーロッパ(NATO)の、しかも多国間の条約に限られていて、それ以外の「相互防衛条約」は、基本的にすべて個別的自衛権にもとづいて協力しあう関係でしかありません。
「そんな話、はじめて聞いたぞ」という方もいらっしゃるかもしれませんが、アメリカが各国と結んでいる条約の条文を見れば、それは疑いようのない事実なのです。
たとえばNATOの条文(北大西洋条約)には、ある加盟国が攻撃を受けた場合、それを全加盟国に対する攻撃と認識して、
「個別的または集団的自衛権を行使し、兵力の使用を含んだ必要な行動をただちにとる」
と書かれています(第5条)。これが「集団的自衛権」にもとづく相互防衛条約です。
一方、日本の新安保条約(第5条)などアジア地域の条約には、特定地域(たとえば太平洋地域など)内での加盟国への攻撃が、
「自国の安全を危うくするものであることを認め」
「自国の憲法の規定と手続きにしたがって、共通の危険に対処する」
としか書かれておらず、必ず相手国を守るために戦うとは約束されていません。それがあくまで「個別的自衛権にもとづいて協力しあう関係」でしかないことは、明らかなのです。
安保改定交渉の真っ最中だった1959年6月に、本国の国務省からマッカーサー大使に送られた電報には、この「自国の憲法の規定と手続きにしたがって」という表現について、「〔われわれ国務省が〕長期にわたる慎重な研究の結果、到達したものだ」と書かれています。つまり「相互防衛条約」とはいいながら、相手国への最終的な防衛義務は負わない条文を、意図的に考えだしたということなのでしょう。
さらに連載記事<なぜアメリカ軍は「日本人」だけ軽視するのか…その「衝撃的な理由」>では、コウモリや遺跡よりも日本人を軽視する在日米軍の実態について、詳しく解説します。
矢部 宏治
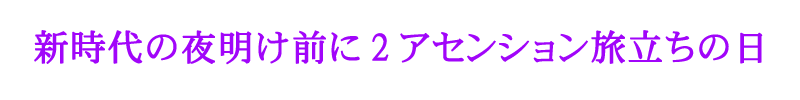



コメント