大企業に「絶対有利な税と制度」を築き上げ、国民生活に負担を押し付ける「自民党の大罪」政治が失われた30年を作った。
昭和から平成初期までは、景気向上時は国民も肌感で感じられ、実質賃金はバブル崩壊を経て1996年にピークを付けるまで右肩上がりで上がってきた。労働者にとっては、今より有利な環境が背景にあったのかもしれないが、逆に言えば、それは経営層や株主からみれば「不遇の時代」だった裏返しでもある。
低賃金は国民生活より経済界を優先した結果
そのため、経団連はじめ財界は、法人税率の引き下げや労働規制の緩和を政府に要求してきた歴史がある。1994年から導入された小選挙区制により、与党執行部の権力が増して、ピンポイントに効率よくロビー活動ができるようになったからなのか、以降、企業が負担する法人税率はどんどん引き下げられ、雇用規制も「働き方改革」として緩和された。
その間、国民が負担する消費税が「直間比率の是正」を理由に新設され、税率もどんどん引き上げられていった。因果関係はともかく、結果的に実質賃金は1997年以降、右肩下がりで、特に直近では24ヵ月連続で下がっている。
その一方で、企業は最高益の更新が相次ぎ、両者の違いは鮮明だ。
歪んだ再配分によってもたらされた「分断」
特に税制の変更が与える影響は大きい。静岡大学元教授で税理士の湖東京至氏がいう。
「国民なら誰しも中学校の時に、『税の役割は富の再配分』と習ったはずです。 昭和の終わりまでは確かに企業や個人など、所得が高いほど税負担が大きかった一方で、これらの節税のため、経費や消費に回るお金も多かった。中間層以下では税や社保などの公的負担が今ほど重くなく、税による富の再配分機能が生きていて、中間層の分厚い骨太の経済構造と言って良かったと思います。
しかし、今の税制は再配分とは逆で、消費税と法人税の関係をみても、ないところから取って、すでに余っているところへさらに配るような税制になっているのです。
税は、本来、儲かった企業や個人の余剰部分を課税対象とし、結果的に格差を緩やかにして、多くの国民が安心して暮らせる状態を『公平性』や『安定性』と見て、それを実現するための、再配分装置です。
しかし、公平性が“税率”を指すといった間違った解釈をしてしまうと、余剰マネーが大きい富裕層や大企業ほど、再投資も含め、格差はどんどん拡大してしまいます。その結果、価値の高いものの物価はさらに上がり、中間層以下の生活水準はどんどん貧しくなり、結果として社会は不安定になってしまいます」
森永卓郎氏が直言
「書かずに死ねるか」と森永卓郎氏、日本衰退の真相が書かれている
その税率や公的負担についても、公平どころかむしろ、富裕層の方が安いと指摘するのは、『書いてはいけない――日本経済墜落の真相』の著者で経済アナリストの森永卓郎氏だ。
「国民負担率は直近で46.1%――これは財務省が公表している数字です。一方で、大金持ちは資産管理会社を作っているので、日常生活の一部は経費で支払え、消費税分ですら、税額控除で還付されるので支払わなくて済む。株の譲渡益なら20%です。
これは『1億円の壁』とも言われ、1億円を境に所得が増えるほど、実際の税負担率が下がるとされ、岸田総理は2021年の総裁選で『壁』の解消を訴えていたほどですが、いまだ未着手です。 実際の負担率は大金持ちの方がむしろ軽いのです。政治家は口では賃上げ要請など、労働者に寄り添う姿勢を見せますが、実際の制度では結果的に企業やお金持ちのプラスになることしかやっていないのです」(森永氏) これでは国民が疲弊して経済が弱くなるのは必然かもしれない。格差拡大と言われて久しいが、これはたまたまではなく、国が政策として作った制度がもたらした結果なのか。
「税制大綱」は企業優遇のオンパレード
前出の湖東税理士が続ける。 「毎年年末に発表される税制大綱をみてください。財政難や社会保障を理由とした国民への負担増に目が行きがちですが、実は企業向けでは減税や特例のオンパレードです。
例えば、賃上げした企業に法人税を減免する『賃上げ税制』は、安倍政権時代の2013年から導入されていますが、そもそも、赤字企業には恩恵がなく、企業にとっては、減税の恩恵分より賃上げの負担分の方が大きい。単純に業績が良く賃上げできる企業に節税の恩恵を与えているだけで、カツカツの中小企業には恩恵がないのに、『効果が不十分』という理由で、この制度は拡大され続けています。
省庁も企業向けの補助金ばかりで、これらの原資の大部分は国民からの税金です」
国は誰のために政治をやっているのか
税収に占める法人税の割合は1988年には36%だったが、2023年には21%にまで低下した。企業は労働者の人的リソースでその活動が成立しているのに、社会福祉の負担割合は少ない。そして、その間、「安定財源」だとして大幅に増税されたのが、消費税だ。
「安定財源というのは、徴収する国からの見方で、取られる国民や価格転嫁が難しい中小企業から見れば、苦しい時も容赦なくとられる極めて過酷な税です。にもかかわらず、国はさらなる税率引き上げを考えているのです。 国は同じ一般会計に入る税であっても、国民から取る税は、『財政難で増税は仕方がない』と負担の論理を採用し、減税や給付は『貯金に回るから』などの理屈で、すぐに打ち切ります。
一方で、ただでさえ儲かっている企業には、『国際競争力のため』などと配慮の論理が採用されて減税され、内部留保(貯金)に回ろうが、量が足りないという理屈でむしろ拡大されます。 政府は税に対する基本スタンスを、国民向けと企業向けで使い分けているのです。税制の扱いの差をみれば、国が誰のために政治を行っているか、よくわかります」(湖東税理士)
内部留保を貯めこむ弊害
小泉純一郎元首相と大手人材会社会長を務めた竹中平蔵氏 photo by gettyimages
前回記事でも指摘したように、1998~99年に大幅に法人税率を引き下げて以降も、段階的に引き下げられ、企業はお金を貯めやすくなった。好調企業でも、部門ごとに子会社化すれば、人件費の抑制が可能となる持ち株会社制が97年に解禁され、小渕政権や小泉政権では、雇用規制が大幅緩和され、結果的に人件費は抑えられるように制度変更された。
経済ジャーナリストが言う
「特に労働者派遣の規制緩和は、実質的に解雇権と中間搾取を国が認めたようなもので、不景気時のリスクを非正規雇用者に一方的に押し付けるようなものです。そして、同じ会社内でも、部門ごとに子会社化(分社化)すれば、人件費を抑えられるので、企業の利益成長と賃上げの相関性ますます落ちます。
国が会社内に賃金が上がらない階層の身分制度と垣根を作ったようなもので、その政策のおかげで企業の利益率が上がるのは当たり前で、賃上げができず、国内消費が冷え込むのも当たり前なのです。失われた20年や30年と言うのは、デフレ“マインド”ではなく、単純に国の政策の結果、ない袖が振れなくなった人が増えただけでしょう」
そのようにして、企業があげた利益の一部は内部留保となり、自己資本比率を高めるが、この数字に果たしてどこまで意味があるというのか。
「法人企業統計の減価償却の数字をみても、内部留保が設備投資に回っているのは限定的とみられ、資金調達と経営上のリスクが低くなるといった評価を受ける程度です。企業にとっては、財務基盤が良くても、成長性が低いと評価されないのはPBR(株価純資産倍率)1倍割れの企業の多さをみても明白で、どの道、経営危機になれば、すぐにお金はなくなってしまいます。
リスク回避についても、コロナ禍では、大手企業でも賞与が容赦なく減らされたりして、結果的に内部留保にはほぼ手が付けられず、黒字を確保していた企業も少なくありません。そして、コロナ禍を含め、『誰も幸せにしない数字』が毎年過去最高ペースで積みあがっているのです」(経済ジャーナリスト)
経営層と株主以外「全員負け組」
労働分配率を見ても、アベノミクスが始まった特にこの10年では、中小企業は10%低下し、70%に。大企業に至っては50%から39%となり、20%も下がった。
「労働分配率は景気と逆相関するのが常ですが、下限がないのが本来おかしく、好業績時にその分、下がってしまうのでは、労働者は好景気の恩恵を受けられないことになってしまいます」(経済ジャーナリスト) 賃上げが進まない理由に、企業はアンケートで「価格転嫁が進まないから」「先行き不透明だから」とお決まりのように弁解しているが、増え続ける内部留保を考えると、額面通りには受け取るのは難しい。そもそも、将来は見通せないのが当たり前だ。
企業規模による労働分配率の差を見てわかるのは、中小企業は大企業にマネーを吸い上げられて賃上げの原資が十分ではなく、大企業は貯蓄と株主配当に走る、という構図だ。もはや、経営層と株主以外は「全員負け組」の社会とも言えそうだ。
企業の「最終利益」は労働者の犠牲のバロメーター
「残念ながら、企業業績と賃金がリンクするのは不景気や会社が傾いたときだけで、会社が儲かった時に賃金が増えるというような昭和時代のような相関はすでにありません。
もともと、賃金は『上げたくても上げられない』のではなく、本音は『株主利益のために、賃金を上げたくないから、上げなくて済むように国が作ってくれた制度を利用しているだけ』といったところでしょう。もっとも、これは企業が悪いのではなく、企業の声ばかりを聞く政策に偏った政治に問題があるのではないでしょうか」(経済ジャーナリスト) 前出の湖東税理士も言う。
「よく『経済が好調で企業は儲かっているのに、なぜ賃金に還元しないんだ』という議論があります。確かに昭和時代では、『儲かった』と言えば、それは売上や粗利のことを指し、これは賃金の原資になる。でも、今、儲かったと言えば、税引き後の最終利益を指します。両者はまるで違うのです。最終利益は賃金や雇用を抑制し、時にはリストラして、やっと確保できる数字でもあり、この数字は労働者の犠牲のバロメーターという側面もあるのです」
厚労省の資料でも「経済成長」と「賃金」は逆相関
厚労省「経済成長率と賃金上昇率の関係ーバブル崩壊後27年間(1994~2021)の動向ー」より
それでも国は『経済のため』と、“経済”を旗印にあらゆる政策を進めている。
「経済とは豊かさであり、『経済成長』と『賃上げ』はいまだに無意識にリンクして、相関性があるものと決めつけられている節があります。
しかし、この認識は全く事実に反しており、この間違った認識を持つこと自体、実は非常に良くない。
『経済』という単語がGDP(国内総生産)を指すなら、物価を反映した実質GDPと実質賃金は20年以上、むしろ逆相関していて、これは厚労省の資料でも指摘されています。“経済”は良くなっても、賃金環境は現に、悪化の一途を辿っており、国民に負担を押し付けた結果の企業の繁栄と言えなくもないのです」(前出の経済ジャーナリスト)
長年続く「国民生活を犠牲」「企業を支援」する政治
それなのに、国は企業向けに減税特例や補助金、規制緩和やインバウンド政策など、さまざまな優遇措置や政策を推し進め、不景気時は何十兆円もの補正予算を組んで、その大部分を『経済対策』として、企業部門にバラまいているのが実情だ。
「国民向けの減税や給付と違い、経済対策の支出は自動的にGDPに計上されるため、確かに“経済”は向上します。
しかし、その“原資”は言うまでもなく、大半は国民が納めた税金です。国の経済対策が、賃上げしない企業部門に偏っていると、それは経営者層と株主の利益の為に国民生活を犠牲にしているのと一緒です」(前出の経済ジャーナリスト) 財政難を理由に生活が貧しくなっている国民からは増税して、今度はそのお金を経済対策と称して、企業にバラまく…。果たして、政府自民党は、本当に国民の生活の向上を目指しているのか。はたまた国民に負担増を押し付ける言い訳の表明が仕事だと考えているのか…。
賃上げを左右するのは「制度変更」
いずれにせよ、賃上げスパイラルは経営者の温情や政治家の口先介入で都合よく訪れるものではない。重要なことは、経済成長で“原資”が貯まること以上に、それが分配される仕組みがあるかないかだ。それは現状で企業に有利な制度や税制を、国民に有利な制度に戻せるか、その『制度変更』の有無にかかっていると言えるだろう。
「賃金というのは突き詰めると受給バランスで決まりますが、雇用の流動性が低い日本のサラリーマンの賃金は、制度的な要因が大きい。もともと賃上げは経営者の裁量や温情によるものではなく、制度を含めた経営環境によって、経営者にとっては、いわば嫌々、もたらされるものです。そうでないと、管理部門やバックオフィスなど付加価値を生みにくい職種の賃金がずっと据え置きになってしまう。
月の基本給が下がらないのも、理由なく解雇ができないのも法律で決められているからです。企業にとってこれらの規制は、労働生産性を下げる要因にしかなりませんが、仮に、これらの規制を『企業支援』のために緩和し、その結果、失業者や低賃金労働者が増えればどうなるか。企業にとっては最終利益が増える半面、マクロ経済では彼らが寄与していた何十兆円もの消費市場が消失し、社会も不安定化してしまうでしょう。
上記は極端な例ですが、もともと経済は付加価値を創造する企業とそれを消費する国民という両輪のバランスで成長していきます。財界が要望する人件費抑制に繋がるような政策に偏っていれば、賃金は上がらず国民が困窮し、消費が落ち込んで大した経済成長もしなくなるのは当然です」(経済ジャーナリスト) 果たして賃上げに繋がる「制度変更」はあるのか──。
本多 慎一(ライター)
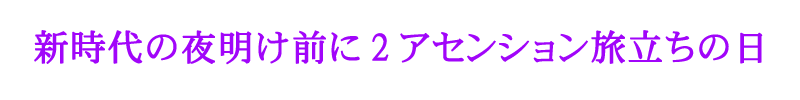



コメント