【ニッポンの農業危機】2030年までに農業従事者は半減、農地も2割減に
東北地方の耕地面積を上回る規模が“消滅”する。国の減反政策の先に見えてくる深刻なコメ不足が日本を襲う!
スーパーで買い物をするたびに痛感させられる物価高。とりわけ高いと感じるのがコメや野菜・果物などの農産物だ。いずれ供給が追いついてくれば元の価格に戻ると期待したいところだが、今後2割もの農地が“消滅”するという衝撃の推計を農林水産省がまとめた。日本の農業は一体どうなるのか──。
日本が抱える重大課題に斬り込んだ新書『縮んで勝つ 人口減少日本の活路』が話題のジャーナリスト・河合雅司氏が解説する【前後編の前編。後編を読む】
* * *
「令和のコメ騒動」は新米が流通しても収まる気配がないが、今後さらに事態が深刻化しそうである。農地の激減が根本原因となってきているためだ。
農林水産省がこのほどまとめた推計によれば、農業経営体は2020年の108万から2030年には54万へと半減する。
内訳としては、法人等団体は4万から5万に増えるが、主業経営体(個人経営体)が23万から11万に減り、準主業経営体(農業外の所得が主で、60日以上働く65歳未満の世帯員がいる個人経営体)と、副業的経営体(60日以上働く65歳未満の世帯員がいない個人経営体)の合計は81万から38万に落ち込むと予想している。
経営体が減るにつれて、経営面積(耕作面積)も約92万ヘクタール減る(約35%減)と見込んでいる。全国の耕作面積は427万2000ヘクタール(2024年7月15日現在)なので、2割ほどの農地が“消滅”するということである。これは東北地方の耕地面積(80万9600ヘクタール)を大きく上回る規模である。インパクトの大きさが理解できよう。
今回の推計は、初めてコメ、麦、大豆などの土地利用型作物、露地野菜、施設野菜、果樹の4品目に分類した見通しも示したが、土地利用型作物の経営体は2020年の60万から2030年には27万へと55%減る。果樹も13万から6万5000へと半減する。
この結果、土地利用型作物は耕作面積が74万ヘクタール減となる。果樹は9万ヘクタール減で、これら2品目だけで減少面積全体の9割を占める。
一方、露地野菜と施設野菜については主業経営体こそほぼ半減するが、耕作面積は元の数字が大きくないこともあって、露地野菜が8万ヘクタール減、施設野菜は9000ヘクタール減にとどまる。これら野菜に関しては生産が大きく減少するという事態は避けられそうだ。
“コメや果物が贅沢品”になる日が来るのか
食料の多くを輸入に頼る日本は国際情勢の影響を受けやすく、食料品の値上げラッシュの先が見えていない。こうした状況下で国内生産が縮小したならば、食料品価格はさらに高騰するだろう。いまにコメや果物は庶民にとって“贅沢品”となるかもしれない。それどころか、コメは主食であるだけに食糧危機まで懸念しなければならなくなる可能性さえある。
なぜ土地利用型作物は、かくも減る見通しとなってしまったのだろうか。
土地利用型作物は面積あたりの収益性は低いが、農地の集約を図りさえすれば生産性の向上が見込める。農水省のデータでコメに関する生産コストと所得の割合をみてみると、15~20ヘクタール以上になると所得が生産コストを上回るようになる。これは、利益を上げるには最低でも15~20ヘクタール以上の農地が必要ということである。50ヘクタール以上となれば所得が跳ね上がるように増える。
日本の場合には農地が分散して小規模になっているというケースも少なくないが、生産性向上のための手立てが分かっているのだから実行に移せばいいだけの話とも思える。それでも土地の集約が進まない背景には、人口減少と就業者の高齢化の影響がある。
土地の集約が進まない背景にある少子高齢化
土地利用型作物に関して、今回の推計における経営体の予測を実数で見ると、準主業経営体・副業的経営体が50万から22万へ減ることが全体の数値を押し下げた。これに合わせて、準主業経営体・副業的経営体の耕作面積は80万ヘクタールから36万ヘクタールへと大きく減る。主業経営体も84万ヘクタールから40万ヘクタールへと激減する見通しだ。
副業的経営体は70代以上が72.2%、60代が26.4%と全体の98.6%を占めている。準主業経営体も70代以上が40.5%、60代が31.7%と計72.2%となっており、50代以下は27.8%に過ぎない。
コメの場合は準主業経営体と副業的経営体が48%、果樹類では47%と割合が大きく、その多くが60代以上ということだ。
これらの数字からは、若い世代への代替わりが進まず将来展望が開けないため、土地集約に向けた一歩がなかなか踏み出せない事情が透けて見える。
若い世代への引き継ぎが進まないのは、いくつもの要因が重なってのことだが、少子化でそもそも継承する若者が少なくなったことが大きな理由だ。
いまやどの職業も人手不足だが、農業の新規参入はとりわけハードルが高い。まとまった土地を必要とするなど初期投資にお金がかかる上、土地ごとに自然条件が異なって栽培ノウハウを身に付けるに時間を要する。家業を継ぐ親元就農(おやもとしゅうのう/農業経営主が三親等以内の親族)など、農業と何らかの縁がある人でないとなかなか難しい現実がある。
しかも親元就農の対象となる人自体が減っている。出生数の減少は基幹的農業従事者の夫婦においても例外ではなく、生まれた子どもがすべて家業継ぐわけでもないだろう。
農水省のデータがこれを裏付けている。
2018年の新規就農者は55万8000人だったが、2023年は22%少ない43万5000人だ。このうち新規自営農業就農者(親元就農)は、42万7000人から29.2%少ない30万3000人となった。親元就農者のほうが、減り方が大きいのだ。
親元就農の約6割はコメの生産に従事しており、この落ち込みがそのまま土地利用型作物や果樹の減少につながっているのである。
農業が「苦労の割に儲からない仕事」となっているワケ 農産物の適正 な価格形成と消費者支援のために検討すべき“食料品を消費税の対象から除外”
2030年までに東北地方の耕作面積を超える規模の農地が“消滅”する──先ごろ農林水産省がまとめた推計が波紋を呼んでいる(詳細は前編記事〈【ニッポンの農業危機】2030年までに農業従事者は半減、農地も2割減に 東北地方の耕地面積を上回る規模が“消滅”する〉参照)。農産物の国内生産を維持するには農地の集約などを進める必要があるが、人口減少と高齢化の影響で若い世代への引き継ぎが進まず、将来展望は描けないままだ。
日本が抱える重大課題に斬り込んだ新書『縮んで勝つ 人口減少日本の活路』が話題のジャーナリスト・河合雅司氏が、日本の農業の危機を踏まえて、現実的な打開策について提言する。
* * *
全国の農家で若い世代への引き継ぎが滞っている大きな要因は、少子化で継承する若者が少なくなったことだけではない。農産物の価格転嫁の動きが鈍いことも挙げられる。
食料品というのは、言うまでもなく最も基礎的な生活物資だ。なるべく安く購入したいとの心理が多くの消費者に働くのは自然なことである。
一方、農産物は消費者の手元に届くまでにいくつもの流通過程を踏むため、各段階の取り引きにおいてこうした消費者心理を受けた価格競争が起きやすい。生産者は価格転嫁をしづらい環境に置かれているのである。
肥料や飼料の節約には限界があるのに、思うように価格転嫁が進まないとなれば、そのツケは生産者に回る。肥料や飼料の高騰が著しい昨今のような局面においてはなおさらだ。収益が落ち込み農業経営への影響が大きくなる。農業が「苦労が多い割に儲からない仕事」となっているのでは、若い世代が就農をためらうのも当然だ。
農水省のデータからは、「儲からない農業」を避けようという動きも見て取れる。年に複数回の生産が可能で面積当たりの付加価値が大きい施設野菜や露地野菜への集中が、土地・資金を独自調達した就農者や企業の新規参入を中心に目立つ。コメづくりより利益が得やすい作物へと人が流れているのである。
コメづくりは規模を拡大しないと儲からない
農業従事者「激減」で手遅れになる前に
果樹も「苦労の割に儲からない仕事」という点では同じだ。温州ミカンなどは中山間地域での栽培が多く、急傾斜の段々畑に軽トラックが入れないところもある。傾斜地での作業の危険性が高いため機械化も困難で、労働生産性が向上しづらい。
リンゴなどは比較的平坦なところでも栽培できるが、枝の広がった背の高い樹木が不規則に並び、そうした木々を回り込む作業が必要なため、こちらも機械化が進みづらく作業に手間がかかる。作業時間が長くなりがちなのだ。果樹は機械化が最も遅れている分野ともされている。
しかも、果樹は短期に労働のピークが集中するという特徴がある。人口減少で人手不足が拡大し続ける状況下では、短期労働力を一気に集めることは非常に難しい。未収益期間が長いこともあって、新規参入が進んでいないのである。このままでは土地利用型作物や果樹の経営体の落ち込みに歯止めがかからないだろう。
影響はそれだけではない。耕作面積の大規模な縮小は畜産農家にとっても大きな打撃だ。
畜産も飼料費の高騰が経営を圧迫するようになってきており、国産を増やすことによるコスト削減が課題だ。しかしながら、畜産経営は規模の拡大を図っており、飼料生産を拡大する余地が少なくなってきている。
打開策の1つとして、耕種農家(植物を栽培する農家の総称)に飼料を生産してもらう耕畜連携が期待されているが、耕作面積が急速に減ったのでは思うように計画が進まなくなる。
こうした深刻な状況に対して、農水省は既存経営体の規模の拡大や新規参入の強化といった取り組みに加えて、【1】農地面積や労働時間当たりの収量拡大(生産性向上)、【2】単位面積や収量当たりの収益性拡大(付加価値向上)を掲げている。むろんこのような農業経営の構造転換は重要なのだが、2030年までの激減ぶりを考えると、残り時間が足りない。
農業に従事する人が極端に減ってしまってからでは手遅れである。優先すべきは、農産物の適正な価格形成の実現であろう。
「食料品=消費税ゼロ」も選択肢
先述したように、農産物の価格転嫁はなかなか難しく、その皺寄せは生産者に行っている。こうした現状を改めるには、適正価格の形成に向けて関連業界を含めた体制作りを急ぐ必要がある。
とはいえ、多くの国民が物価高に苦しんでいる現状を看過することもできない。国民負担率の高まりを受けて、暮らしにゆとりのない人が増えている。今後は低年金者や無年金者の増加も懸念される。
こうした点も勘案すれば、適正な価格形成を図るのと同時に、消費者への支援にも取り組まなければならない。
農業生産者と消費者の双方の暮らしを守り、かつ食料自給率の低下を防ぐには思い切った政治決断が不可欠だ。食料品を消費税の課税対象から除外して「ゼロ税率」にすることも選択肢となろう。
農水省の今回の推計を見る限り、「日本はすでに食料安全保障上の危機に直面している」と認識することが必要だ。補助金を支給するといった小手先の対応では如何ともしがたい局面に突入している。
「食」に関するあらゆる課題にメスを入れ、「人口が減っても持続する農業」と「安定的な食料供給」が同時に実現するよう社会の仕組みを根底から作り直すことが求められる。
河合雅司(かわい・まさし)/1963年、名古屋市生まれの作家・ジャーナリスト。人口減少対策総合研究所理事長、高知大学客員教授、大正大学客員教授、産経新聞社客員論説委員のほか、厚生労働省や人事院など政府の有識者会議委員も務める。中央大学卒業。ベストセラー『未来の年表』シリーズ(講談社現代新書)など著書多数。話題の新書『縮んで勝つ 人口減少日本の活路』(小学館新書)では、「今後100年で日本人人口が8割減少する」という“不都合な現実”を指摘した上で、人口減少を前提とした社会への作り替えを提言している。
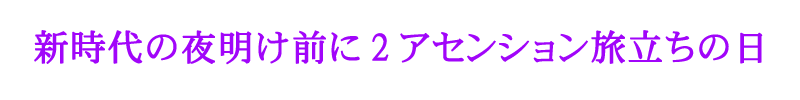





コメント