各地の大規模な道路陥没のリスクを高めたのは「道路特定財源」を廃止したことも一つの要因だった?
財務省の緊縮予算が招いたツケ!責任は財務相にある。
八潮市の道路陥没事故の原因などからもわかるように、いまや全国各地の道路が陥没している(今後陥没の危険がある)と指摘されています。
月28日、埼玉県八潮市の県道松戸草加線(54号線)で道路の大陥没事故が発生。昨年9月4日には千葉県市原市でも国道16号で大規模な陥没が起きている。関東にお住いの方ならば、まだ記憶に新しいのではないだろうか。
国道16号の陥没は幅15m、長さ5.5m、深さ8.5mの規模で範囲は上下4車線におよび、通行止めの解除にも2日半を要した。
国道16号の陥没の原因について千葉国道事務所は、陥没箇所を横断する銅製の雨水管の腐食にあると説明する。なお、この雨水管は布設から60年経過していたという。
なぜ、いま全国各地の道路が陥没しているのか? 原因は地中の下水管や雨水管の老朽化にあり。 | KURU KURA(くるくら)
参考
埼玉 八潮 道路陥没事故 発生から1週間 男性は依然安否不明 捜索急ぐ 節水呼びかけ 生活面の影響は | NHK | 事故
「雨水管」
嘗ての日本では、 下水道 と連結され、雨水と下水と一緒に処理される「合流式」が取られていたことから、雨水管の設置や管理は地方自治体の下水道の担当部局が担当していることが多い。 現在新設されている下水道では、雨水と下水を分離して雨水を河川等に放流する「分流式」が主流となっており、新たに雨水管網が構築されるようになっている。
合流式も分流式も含め「下水道」は一般的には、市町村の下水道部門や公共施設の管理部門が下水道の運営と保守を担当しているそうですので、自治体によっては財源がそもそも不足している地域もあるのは当然です。
それに加えて、定期的な道路整備・維持管理がおろそかになっていることは明らかで、財源の乏しい地方の担当部署に責任を押し付けず、陥没のリスクが高い道路などから順番に、雨水管ともどもの土木工事が必要なのではないでしょうか。
また、これに関しては財務省などにも原因がある、という意見も出てきています。
■道路特定財源の廃止
悪評高い「ガソリン税」は(二重課税という批判がありますが)、もともと使い道が道路整備・維持管理等のためだけに限られる「道路特定財源」でした。同様に「自動車重量税」も受益者負担の原則で、道路整備・維持管理目的に使われていたようです。
21世紀に入ってから小泉内閣のときの「構造改革」の流れのなかで、2009年以降は「道路特定財源」は廃止され、使い道が限定されない「一般財源」に組み込まれることになりました。
具体的には2005年に当時の小泉内閣の時の政府・与党が決めたことだったようです。
小泉構造改革って、自民党は結局こわれず、霞が関もこわれず、結果的に日本の強みを悉く壊しただけでしたね。
■道路特定財源制度
自動車の利用者が道路の維持・整備費を負担する、受益者負担の原則に基づく、かつて存在した日本の目的税(特定財源)。2009年4月30日に「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律案」が成立したことにより、2008(平成20)年度限りで廃止された(一般財源化された)。
ガソリン税や自動車重量課税が国土交通省の道路特定財源だった頃は、ガンガン道路を作り、補修もして、民間にお金が流れていた。それを一般財源化したことで、道路一つ作るのも直すのも、道路局長が財務課長に頭を下げて説得しなければならなくなったのが現在の構造なのだそうです。



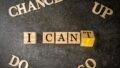
コメント