セルフ式うどん店で「幼児が火傷」→親が“店の責任”を主張し物議 親の管理不足か、店の安全対策ミスか?
セルフ式の場合親の管理責任の割合が高い。米国では・・・。
セルフ式うどん店で幼児が火傷
Threadsでセルフ式うどん店の投稿が話題になっています。
セルフ式うどん店で、親が目を離したときに幼児が火傷し、親が店の責任だと主張している事案について書かれたものです。「何でも店のせいにするのは違う」とし、「火傷のリスクがある場所に幼児を連れていったことが無謀」ではないかと、述べられていました。
これに大きな反響があり、賛同する返信がたくさん寄せられています。
「親御さんの注意ミス」「目を離す方が悪い」「何で店のせいなの?」から「未就学児の入店をお断りにすれば良いのかね」「アメリカならば店側がアウトですけどね。日本では……」といった意見が見られました。
セルフ式のうどん店
セルフ式のうどん店とは、どういったものでしょうか。完全なセルフ式であれば、次のような流れとなります。
店内の入口の注文カウンターで、麺が入った器を受け取ります。天ぷらやおでん、おにぎりなどのサイドメニューを選んで、キャッシャーで会計。
麺を湯に通して温め、出汁をかけ、ネギや生姜、天かす、胡麻などをトッピングして、うどんが完成します。席に座って食事をして、食べ終えたら返却口にまで持って行き、下膳するという流れです。
店が麺を茹でて出汁をかけるところまで行う半セルフも多いです。
セルフ式のメリットとデメリット
セルフ式のメリットは、店からすれば人件費を抑えられるため、リーズナブルな価格で提供できること。注文から提供が早く、食事時間も短いため、回転率も高いです。客からすれば、安くて手軽であることや、トッピングやボリュームを自分で調整できるのが、長所であるといえます。
デメリットは、熱々のうどんや揚げたての天ぷらを客が自ら運ぶため、火傷など事故の危険性があること。狭い通路でトレーを持って移動するので、混雑時に他の客とぶつかるリスクもあります。親が子どもの面倒をみながら、セルフサービスを利用するのも、容易ではありません。
弁護士の見解
うどん店で子どもが火傷する事故は、法的な観点からはどのように考えられるでしょうか。
この投稿で言及されているのと同じ事案かどうかわかりませんが、投稿より1年近く前に、似たような事故を扱った記事が配信されていました。
・セルフ式うどん店で幼児が火傷「どうしてくれるの」 親が目を離した瞬間の悲劇、店の責任は?(弁護士ドットコム)
弁護士の見解では、セルフ式ではない飲食店に比べてセルフ式の飲食店では、子どもに対する保護者の監督責任はより大きいということです。事故が起きた場合には、保護者の過失割合が大きいので、店への責任追及が難しいと述べられています。
ただ、レジ付近に「お子様連れの場合は、目を離さないようにしてください」といった注意書きを設置するなど簡単な措置をしておけば事故は防げたかもしれないとも指摘しています。
子どもに向いていない環境
そもそも、飲食店には子ども向きでない環境があります。
立ち食いスタイルであったり、席がハイチェアやスツール、硬いローテーブルであったり、目の前に熱い鉄板があったり、狭いカウンターであったりする店は、子どもに向いていません。
提供されているのが、おまかせコースのみであったり、食材の対応ができなかったり、分量調整ができなかったりする場合も同様です。
子ども用のイスやカトラリーを用意したり、子どもがモノを落としたり、周りを汚したり、嘔吐したりした時に対応したりと、大人に比べて子どもへのサービスは大変です。
こういった環境やサービス負担の観点から、子連れを拒否する店があります。
セルフ式では、客が熱い料理を運ぶ必要があるため、通常の飲食店よりも火傷リスクが高いです。そのため、特に小さな子どもを連れている場合、ほかの業態よりも注意が必要となります。
どうすれば事故を防げるか
セルフ式うどんで事故が起きないようにするには、どうすればよいでしょうか。
店側の対策としては、火傷リスクの警告をより明確にしたり、子どもが手を伸ばさない位置に受け取りカウンターを設置したり、子連れ用の席を用意したり、店の造りに適した安全対策を施したりすることが考えられます。
親側の対策としては、幼児を抱っこしたり、うどんが運ばれるまで子どもを待機させたりと、子どもがふらふらしないようにしなければなりません。
さらには、全てを店の責任にするのではなく、客側のリテラシー向上も必要だという社会の意識も重要です。
議論を続ける必要がある
セルフ式うどん店は手軽でリーズナブルな食事ができる一方で、火傷などの事故リスクがあることも理解しなければなりません。店側の安全対策と、親側の注意が両立してこそ、より安全で快適な食事環境が生まれます。
利便性と安全性のバランスを考えながら、どのように子どもを守り、共存できるかを今後も議論していく必要があります。


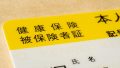

コメント